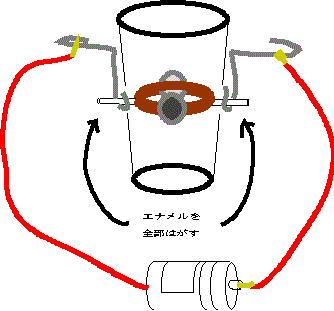
| 「電磁石のはたらき」では,クリップモーター作りが出てきます。教科書では次のような教材が取り上げられています。 このモーターも前々からあるのですが,新しくなった教材はどうもうまく回りません。「モーターの原理を教えるのではないから回ればよい」のですが,回らないのでは興味も半減です。 |
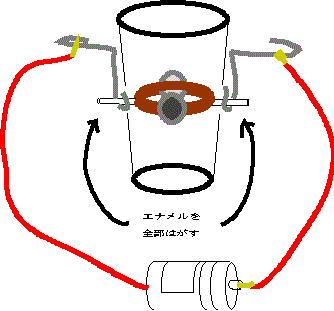 |
|
この特徴は,①磁石が両方にあること,②整流子の部分が2つとも全部エナメルがはがしてあること,です。ふつうは整流子の部分の片方は片側の半分だけエナメルをはがします。これが子供には難しいと判断したのでしょうか。原理的に考えてもこれは間違いです。
そこで,次のような工夫をしたところとてもよく回りました。やっぱり,原理通りの単純な仕組みが一番よいと思います。
|
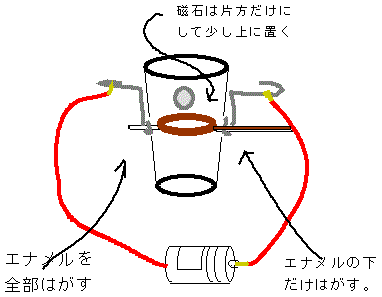 |
| この場合は,電流が磁界から受ける力としてフレミングの左手の法則に従うことになります。 |
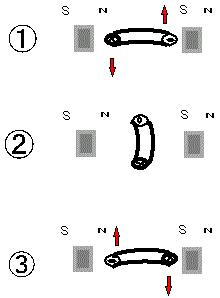 |
教科書では+も-もエナメルがはがしてありますから,左の図のようになり,ブランコ状態になるはずです。 ですから,左図の②から③の状態になるときには,電流が流れないようにすべきです。 |
|
ところが,本校の先生が「教科書通りで動きましたよ。」といわれたので,確認してみましたところ,ゆっくりではありましたが確かに動いていました。
これは大発見です。いったいどうなっているのでしょうか。いろいろ調べたところ,左右の磁石の極が向き合っていることが分かりました。
|
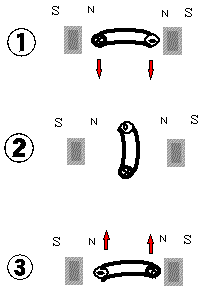 |
すると,①と③の状態の時には同じ向きの力が働くことになります。これならバランスの問題として能率は悪くても回る可能性があります。 |
|
ここまで確認して見えたかどうかは別にして,適当に作っても結構回るものはあるようです。そんなおり愛知物理サークルで講演会があり,小学校の先生にも案内がきたので参加しました。そこで,参加者の先生に疑問をぶつけたところおもしろい話が聞けました。それは
「クリップと銅線の接点が回転の影響で適当に飛ぶので,そのとき偶然接点が離れる。だから,電流が切れた状態になり,結果として回るんですよ。」「時には,エナメルのはがし方が悪くて,適当に絶縁部分が残り,結果的に半分磨いた状態になることもよくあります。」という指摘です。
なるほど!ですから,回るものもあれば回らないものもあると言うことになります。しかし,この理屈から言うと「丁寧に作った子」のものは回らないことになります。これでは,教育とはいえません。やはり,きちんと作った子のものが回ってほしいですね。
そこで,原理通り片側を半分だけ,絶縁をはがし,磁石を真横ではなく,少し上に置くと
|
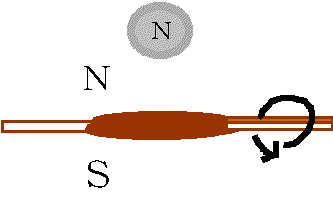 |
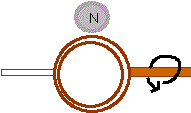 |
横向きになった時点ではコイルに電流が流れませんから,コイルは惰性で回ります。 |
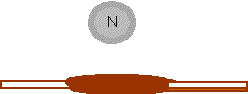 |
反対を向いた時点でもコイルに電流は流れませんから,やはり惰性で回ります。 |
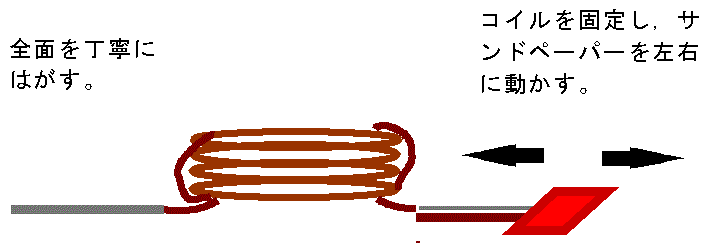 |
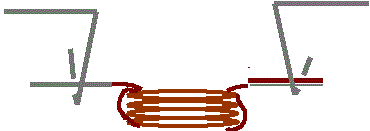 |
|
また,固定した平面において磨くとクリップに乗せたとき,磨いた側が必ず下を向きます。(コイルの重さで,重い方が下を向く。)
③ 磁石は、コイルの少し上に置く。(浅ければカップの底においてもよい。)
クリップモーターも奥が深いですね。何か気付かれたことがあればメールください。
|